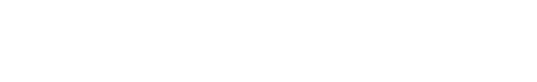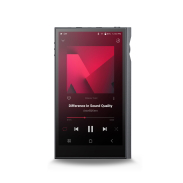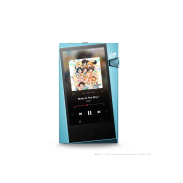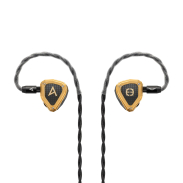──最近の牛尾さんは、正月に公開されたNetflixのアニメ作品『DEVILMAN crybaby』を始め、昨年担当された『聲の形』に続く京都アニメーション/山田尚子監督の新作『リズと青い鳥』(4月21日公開)や、TVアニメ『ブギーポップは笑わない』(年内放送開始予定)、白石和彌監督の実写映画『サニー/32』(2月公開)といった作品の音楽を手がけ、さらにXAI、夢みるアドレセンスといったアーティストへの楽曲提供やアレンジ担当など、実にお忙しいようですね。
ありがとうございます。やはり『聲の形』が大きくて、あれのおかげで知ってくださる方が増えて、いろいろお声をかけていただいています。
──これだけ仕事量が多いと、やはりご自分の中で音楽制作のパターンのようなものが出来上がってくるものでしょうか。
うーん、そうならないようにしてます。劇伴ってメソッドを知っちゃうと手癖で作れちゃう気がしていて。僕は古典的な音楽教育を受けてるわけじゃなく、いろんな技術を使えるわけでもないので、自分の手癖だけでやっちゃうとバリエーションが作れなくて似たりよったりになって、「こなす」感じになっちゃう。それじゃ全然楽しくないので、そうならないようにしてます。劇伴作家って音大を出て弦のスコアが書けてなんでもできて……という人がやるべきものだと思うのですけども、僕はそうではないので、自分が聞いてきた音楽や自分が好きなものに嘘をつかないようにやってるつもりです。

──作品の内容も実写映画とアニメ作品、アニメでも『DEVILMAN crybaby』と『聲の形』ではまったく違いますよね。ご自分の中の切り替えはどうなさってるんでしょうか。
仕事を受ける前にコンセプト・ワークみたいなのをしっかりやっているつもりなので、そういう過程で切り替わっていると思います。適当にやってるととっちらかってしまうと思うんですよね。あれもこれもってなってしまう。筋の通ったものにするには事前のコンセプトワークが大事ですね。
──いろんな方から声をかけられる理由を、ご自分ではどう分析されてます?
僕の場合、お声がけいただいた時から同じチームで同じ釜の飯を食う仲間だという意識で参加させて頂いてます。『サニー/32』だと、自分も白石組の一員であるという大前提がある。と同時に、なんでもかんでも言われたままにできるような技術も知識もないので、自分のキャラクターを出すしかない。その熱意や作家性みたいなものを面白がっていただいているのかな、という気がします。
──いい意味で職人ではない。
全然違いますね。
──アーティストであると。
そうであるといいな、と思ってます。
──作家性を保ちながら、なおかついろんな人に必要とされているなら、理想的な状態ではないですか。
そうですね、今はすごくやりやすいしハッピーな状態だと思いますけど、作家性でお仕事をいただいてると、劇伴ってずっと同じことやってるわけにいかないので、果たして大丈夫なのかって不安になってきますけど(笑)。
──でも実際問題として『DEVILMAN crybaby』と『聲の形』の音楽はまったく違うじゃないですか。
そうなんですよね。僕はやってること一緒のつもりなんですけど、そういうご評価いただいてるのはありがたいです。
──『聲の形』は、それまでの牛尾さん=agraphの音楽の発展型という印象もありましたが、『DEVILMAN crybaby』は全然違う。あれを聴いて、やはり劇伴作家らしくいろんなことができるんだなと思いました。
ああ……そういえば昔(石野)卓球さんに言われたんですけど、すごくマニアックな、現代音楽に近いようなことをやってる一方で、むちゃくちゃポップな、たとえばアニメソングのDJをやったりするような一面がある。そういう二律背反なことををやれるのはおもしろいね、と。それは確かにそうかもしれません。
──最近はアイドルの作曲やアレンジも普通にやってますしね。
はい。確かに。夢みるアドレセンスではちょっとEDM的なアレンジをやったんですけど、細かく打ち込んでいくのは楽しいんです。楽しい仕事でした。

──牛尾さんの制作環境は、基本的に全部ひとりでやってらっしゃるわけですよね。ご自分のスタジオでコンピューターに向かっての作業。
はい。そうですね。
──そんな時の肝になる機材ってなにかありますか。
劇伴ってあと戻りすることが多いので、アナログシンセをずらっと並べてはいるんですけど、それは使わずコンピューターだけで完結させることが多いんですよね。
──再現性が大事ということですね。
はい。なので地味な話になりますけど、サンプリング・ライブラリーかもしれないです。自分で作ってるサンプリングするネタ集。そういうものが肝になるかもしれません。agraphをやるときに実験して作ったものが財産になっていて、それを引っ張ってくることで効率的に作業できるんです。
──agraphの作品を作る時に録りだめてきた音源を引っ張ってきたりアレンジしたり。
そうですね。agraphって自分の中でフラッグシップなんですよ。Mac Proを作っておくと、Mac Book Airのための技術もできる、みたいなもので。だから『SP1000』みたいなハイエンド機種を作っておくと、そこからいろんなものが作れるシナジーが生まれるわけですよ。
──すごく高度な技術が必要な分、毎年のように作れるものではないけど。
「そうですね。すごく時間もかかるし大変なので、今はなかなか手がそっち(agraph)に回らない。あんまり急いで作ってもしょうがないので。『聲の形』を作った時に思ったんですけど、『聲の形』はけっこうagraphを飛び越えた部分があったんですよね。もちろん『DEVILMAN crybaby』でも発見がある。そういう風に循環していくことで、ポジティヴな結果が得られる気がします。劇伴で発見したことをagraphで形にして、agraphで形にしたものを劇伴にして、という。
──なるほど。
僕が名前を出すのもおこがましいですけど、武満徹先生がそうなんですよね。『切腹』(1962年)で邦楽器を取り入れて、その邦楽器の発見から『ノヴェンバー・ステップス』(1967年)に行ってるはずなんで、劇伴が先なんですよね。劇伴で実験して、武満徹名義の作曲に活かしていくという感じだったので、そのやり方は勉強になると思ってます。

──なるほど。『SP1000』の話題になりますが、超高級デジタルオーディオプレーヤーであると同時に、高性能なD/Aコンバーターでもある同機種をしばらくの間牛尾さんにお使いいただきました。牛尾さんの制作環境、あるいは音楽聴取環境の中でお使いいただいて、どんな感想を持ちでしょうか。
あのう……今回使わせてもらった時に聴いたのが、『聲の形』のマスタリング前のミックス・マスターなんです。DSD 5.6MHzなんですけど、それを確認したら……すごかったです。あの作品で僕は自分のピアノの音を録ったんです。
──ご実家で使っていた古いピアノですね。
そうです。子供の頃から慣れ親しんでたピアノ。記号的なピアノの音が欲しかったんじゃなくて、機構として、動く総体としてのピアノの音が欲しかったんで、マイクをピアノの内部に立てて録ったりしたんです。それでも見えない部分ってあるわけですよ。弦を叩くハンマーみたいなのは見えない場所にあるんですが、『SP1000』で聴いたら「ウチのピアノのハンマーはこんな形してるんだな」と思いました。すごく解像度が高い。それに自分のエディットのアラがすごく見えちゃって、がっかりしましたね。
──ふだんご自分がモニターしてる環境と比べても解像度が高い。
高いです。これが一般層に広がったらヤだなあと思いました(笑)。
──解像度が高いって、要は微細なディテールまで全部再現してくれる、ということですか。
うーん、たとえば具体的なことを言えば、『聲の形』はミュージックコンクレートとかコラージュに近い作り方をしたので、今のagraphもそうなんですけど、ハサミを入れるんですよ、波形に。で、波形を途中で切るとパツッとノイズが入っちゃう。僕が使っている「Cubase」というソフトでは「スナップトゥゼロクロッシング」いうボタンがあって、波形は必ずDCオフセットに対してゼロに当たったところにしかハサミが入らないようなモードがあるんですね。でも今回『SP1000』で聴いて、そのボタンを入れ忘れている曲が1曲あることに気づきました(笑)。ゼロクロッシングしてないところで切れてるからサンプルに「パツッ」が乗ってる。それに気づいて、すごい落ち込みました(笑)。
──作ってる段階では気づかなくて、『SP1000』で聴いて初めてわかった。
そうです。
──怖いですね。
イヤです(笑)! あの作品はノイズを扱っているので、それは「味」として、自分が意図した範疇には入ってるんだけど、『SP1000』でモニターしてたら、もうちょっと(ノイズを)聴こえなくしたかな、っていうのはあったかもしれないですね。
──なるほど。
とにかく素晴らしかったです。こんなに音楽の先に演奏している自分の姿を見るとは思わなかった。明らかに自分の息が共鳴板に反響しているんですよ。息のピッチで自分だってわかるから。仮歌を録音する時に切る自分の息と、そこに聞こえる息がぴったりなんで。
──なるほど。
そういう発見が一杯あって。ああこの時オレって今より痩せてる! とか(笑)
──そんなことまでわかる!
イメージですけどね。『リズと青い鳥』の制作で実験したんですけど、キャラクターの前を人が横切るシーンで、実際にスピーカーで鳴らしてステレオマイク立てて、前を横切ってみたんです。それを録音したものをサンプリングしてコラージュしたら、そういう効果が得られたんで、再生物と録音物の間をモノが通るって実験をずっとしてたんですけど、その形が今の自分と違うと思って(笑)。録音したDSD 5.6MHzを『SP1000』で聴いたらそれがわかったという。びっくりしましたね。
──へえ。じゃあ『SP1000』は制作の最終チェックなどに使えそうですね。
そうですね。
──ご自分で使うのはポータブル・プレイヤーなどは……
iPhoneですね。ただ、音楽を作ることと聴くことがそれぞれ別だなって思うと、聴取に愛が持てない時期があったと思うんです。仕事で忙しい時期でテンパっている時に、空いた時間ぐらいは音楽聴きたくない、と思っちゃうというか。
──他人の音楽を聴いていても、ついアラが目についてしまうとか。
逆で、他人の音楽を聴いていると傷つくんです。すごい! と思っちゃって。どんな音楽でも。こんな音楽出来ない、オレはもうダメだ、ってなっちゃう。せっかくの休息時間に傷つきたくないと思って(笑)。

──iPhoneで聴くのと『SP1000』で聴くのでは、体験として違いますよね。
違いますね。全然違う。リスニングとして同じ範疇にない行為だと思いますね。電車の中でイヤフォンでiPhoneで聴きましょうっていうのと、『SP1000』でShureの『SRH1840』で、部屋を暗くして目をつぶって聴くのって全然違う行為ですよね。同じ球を蹴るって行為でも、蹴鞠とサッカーぐらい違う。
──『SP1000』はきっちり音に向き合える手応えがある。
うん、すごくいいと思いました。あのう、ミュージシャンとしてこういうこと言うのは恥ずかしいっていうか良くないんだろうけど、久しぶりに音楽を聴いた気がしたんですよね。自分の音楽だったけど。ここ10年ぐらい、もっとかな、テクスチャーって概念がミュージシャンの中に浸透して、音楽の捉え方が変わったと思っていて。音楽を聴いた時にどういう風に音が鳴っているか、ヴォーカルがあってキーボードがあってギターがあってベースがあってドラムがあって、みたいな構造のあり方とか、鳴ってる音の立体感の捉え方が少し変わったんです。たとえばポーンとピアノが鳴った時に、ここの際の触感とか素材感がどうなんだろうとか。『SP1000』で聴くと、そういう音の存在感とか立体感とか雰囲気みたいなものがすごく感じられたんです。なので浸れる感じがありましたね。『SP1000』で聴くDSD 5.6MHz。すげえなと思いました。その上の11.2MHzも聴いてみたいと思いました。
──なるほど。
ただ『SP1000』の解像度の高さはすごいディテールまでわかるんだけど、その環境とソースのセレクトはちょっと難しいかもしれない。
──向くソースと向かないソースがある。
「あると思いました。明らかにしょぼく聴こえちゃうソースってあるだろうなと。
──その分、すごく精度の高い創作作業ができそうですね。モニタリングの環境だけでも全然変わってくる。
そうですね。強いて要望を出せば、RECスルーできるといいですね。多少レイテンシーはあっていいので。マスターの間に刺せばDSDで聴けるみたいな機能。もちろん変換してるだけなんで意味はないんですけど、でもミックスのチェックの段階ではだいぶ使える仕様にはなりますね。この音のクオリティのままでプロの制作環境に対応した仕様になってくれるとありがたいです、個人的には。
──なるほど。
人間の耳って25歳ぐらいで摩耗していくって言うじゃないですか。有毛細胞がなくなって削れていき、高い音が聴こえなくなっていく。『SP1000』で聴くと残響や空間の広がりがよくわかるんですけど、歳をとって耳が衰えると、十分に聴こえなくなってしまうと思うんですね。ミュージシャンが歳をとっても良いミックスをするには、20歳から25歳ぐらいの時に、良い音を聴いていることが有利に働くように思っていて。その歳ぐらいにスタジオで仕事してる人間はいくつになっても良い仕事をしやすい。良い音を知っているという経験則で、衰えていく有毛細胞を補える気がするんです。なので若い子に機会を増やしたらいいと思いました。若いミュージシャンがこれを聴いたら、リバーブの使い方がうまくなると思います。たとえばベートーヴェンの第九の始まりのフォルテのところとか、初期反射がちょっとあとに来て、そのあとにテールがずっと伸びて行く感じって、普通の家庭環境では聴けないと思うんです。それこそスタジオとかじゃないと。でも『SP1000』ならすごくよくわかる。なので若いミュージシャンに聴かせるようなワークショップとかやったらいいと思うんです。今大きなスタジオで仕事することってなくなっちゃったから、いい音を聴く機会ってなかなかないんですよ。ミュージシャンがスタジオに入って演奏するって機会がないから。みんなベッドルームでアンプシミュレーターを使って直接ラインのギター差し込んで弾いてるだけだから、いい音にあまり接しないんじゃないかと。なのでこれで啓蒙されるのはすごくいいことだと思います。ミュージシャンもこんな音なかなか知らないですよ。1億円のスタジオ買うより全然安いですからね!
──(笑)それぐらいの価値はあると。
うん、いい音を聴くのはすごく大事ですよ。素晴らしいと思いました。
インタヴュー・文/小野島 大 写真/島田 香
(プロフィール)
牛尾憲輔(agraph)
ソロ・アーティストとして、2007年に石野卓球のレーベル"PLATIK"よりリリースしたコンビレーション・アルバム『GATHERING TRAXX VOL.1』に参加。2008年12月にソロユニット"agraph"としてデビューアルバム『a day, phases』をリリース。石野卓球をして「デビュー作にしてマスターピース」と言わしめたほどクオリティの高いチルアウトミュージックとして各方面に評価を得る。2010年11月3日、前作で高く評価された静謐な響きそのままに、より深く緻密に進化したセカンドアルバム『equal』をリリース。同年のUNDERWORLDの来日公演でオープニングアクトに抜擢され、翌2011年には国内最大の屋内テクノフェスティバル「WIRE11」、2013年には「SonarSound Tokyo 2013」にライブアクトとして出演を果たした。一方、2011年にはagraphと並行して、ナカコー(iLL/ex.supercar)、フルカワミキ(ex.supercar)、田渕ひさ子(bloodthirsty butchers/toddle)との新バンド、LAMAを結成。2003年からテクニカルエンジニア、プロダクションアシスタントとして電気グルーヴ、石野卓球をはじめ、様々なアーティストの制作、ライブをサポートしてきたが、2012年以降は、電気グルーヴのライブサポートメンバーとしても活動する。2014年4月よりスタートしたTVアニメ「ピンポン」では劇伴を担当。2017年公開の映画『聲の形』、2018年1月公開の『DEVILMAN crybaby』などの音楽を手がけるほか、アーティストへの楽曲提供やアレンジも担当している。